ビジネス実務法務検定とは、あらゆる業種に通用する法律知識を正しく学ぶことを目的とされた資格です。
ビジネスシーンでは取引先との契約、労働基準法に準じた雇用契約など、法律知識が必要不可欠となります。コンプライアンス(法令順守)能力を身に付け、リスクを事前に回避できる人材は会社の武器として役立つことができます。
ビジネスパーソンとして法律を学ぶことは決して無駄ではありません。そんなビジネス実務法務検定をこれから受けようと考えている方に、級別に試験難易度や出題内容など役立つ情報をご紹介します。
コンテンツ
通称「ビジ法」ビジネス事務法務検定ではないので注意

ビジネス実務法務検定とは、業務を進めるにあたって知っておきたい法律用語を学ぶための検定です。法務関係は総務や人事部が担当しますが、事前知識があればクライアントとの契約もスムーズに進みます。取引先とのトラブルを未然に防ぐためにも、管理職以上のビジネスパーソンは資格の取得がおすすめです。
ビジネス実務と名称が付けられているため事務系と勘違いしがちですが、法務関連の検定です。学習をはじめるにあたっては、事前に出題内容を確認してから進めましょう。
ビジネス実務法務検定3級の難易度は?法律系資格の中では簡単!

ビジネス実務法務検定には3級・2級・1級があります。3級の難易度はどの程度なのでしょうか。法律に関する資格となると、一見難しそうに感じますが、ビジネス実務法務検定3級は比較的簡単な試験と思っていいでしょう。
基礎的な法律の知識を問うレベルであり、合格率が高く難易度は低いと言えます。法律初学者でも比較的合格しやすい資格試験です。
3級の出題内容は?民法中心に基本知識
3級で出題される内容は下記の通りです。
3級で出題される法律
民法グループ→民法・借地借家法・破産法・民事再生法・仮登記担保法
商法グループ→商法・会社法・手形法・小切手法・会社更正法
労働法グループ→労働基準法・労働組合法・男女雇用機会均等法・労働者派遣法
特例法グループ→独占禁止法・不正競争防止法・大店立地法・消費者契約法・割賦販売法・特定商取引法・個人情報保護法・特許法・著作権法・商標法・実用新案法・意匠法
- ビジネス実務法務の法体系
- 企業取引の法務(契約に関すること)
- 債権の管理と回収
- 企業財産の管理と法律
- 企業活動に関する法規則
- 企業と会社の仕組み
- 企業と従業員の関係(労働契約・雇用に関すること)
- ビジネスに関連する家族法
3級の試験問題で中心となるのが民法と商法、会社法となります。そのなかでも重視すべきなのが民法の分野です。
3級試験の出題範囲の中で100点満点中、約50点が民法の分野に関わる問題となり、試験全体の中で構成が高いのがわかります。テキスト全体の学習が必要ではありますが、特に配点の高い民法の分野に力を入れて民法を勉強をしましょう。
3級の合格率は?平均60~70%以上!
ビジネス実務法務検定試験3級の合格率は平均60~70%です。ここ数年で見ると2020年、2021年ではおよそ7~8割以上の方が合格していることが分かります。基礎的な法律の知識を問うレベルのため、はじめての挑戦でも合格しやすいと言えます。
| 2020年度(第48回) | 2021年度(第49回) |
| 75.7% | 87.3% |
参照:東京商工会議所 検定試験情報
3級の合格基準は?7割正答できるかどうか
制限時間は90分で、100点満点中70点以上取れば合格となります。
出題される内容は基礎的な要素となり、身近に感じることが多いです。日常生活の中でも起こり得るトラブルを考えながら学習することができます。
ビジネス実務法務検定3級は一夜漬けできる?やや不安
3級は合格率が高く、難易度は低い試験と言えますが、出題範囲が広く一夜漬けて合格を目指すのはやや不安です。おすすめではありません。
3級の合格に必要な平均学習時間目安は60時間と言われています。計画的に学習を進めていくことで理解を深めることもできますので余裕をもって勉強を始めましょう。
ビジネス実務法務検定2級の難易度は?
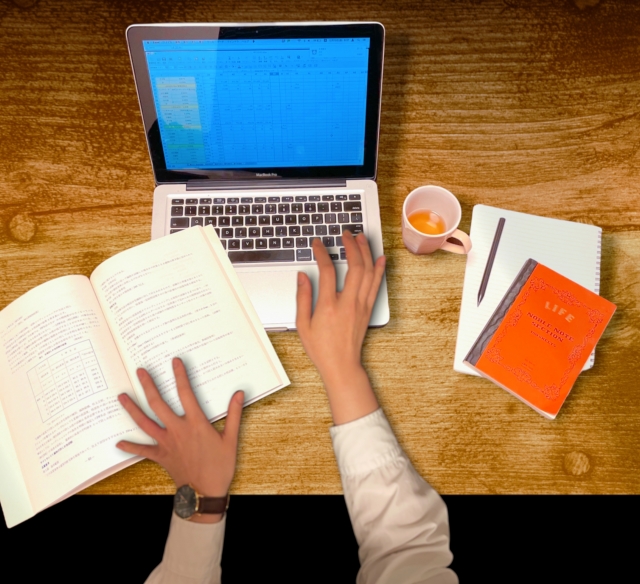
3級は難易度が低く、比較的合格しやすいビジネス実務法務検定ですが、2級になると難易度はどれほど上がるのでしょうか。
2級は独学でも合格が可能なのかも説明していきます。
2級の出題内容は?実務に使える技術まで問われる!
法律に対するより深い理解度と、実務に支障のない応用スキルが求められます。2級の出題内容は3級の内容よりもさらに広くなり、学ぶべき法律の数が追加されます。
3級に追加される法律
民事保全法、金融商品取引法、労災保険・雇用保険・年金・医療保険、下請法、景品表示法、医療品医療機器等法、条例や行政、公害関連法による規制、行政手続など
全体の内容は下記の通りです。
- 企業取引の法務
- 債権の管理と回収
- 企業財産の管理・活用と法務
- 企業活動に関する法規制
- 株式会社の組織と運営
- 企業と従業員の関係
- 紛争の解決方法
- 国際法務(渉外法務)
2級の合格率は?平均は40%だが…
ビジネス実務法務検定2級は、3級の合格率60%~70%と比べると大きく合格率が下がり、平均40%といわれています。
しかし、その合格率は上がったり、下がったりを繰り返しており、必ずしも一定ではありません。16.7%まで低下をしたこともあり、問題内容によっては合格率が一気に落ち込む可能性があります。
2級の合格基準は?7割正答できるかどうか
3級と同じく、2級の合格基準は100点満点中70点を取れば合格です。
試験範囲が3級と比べ広範囲となるので、傾向と対策を立てて勉強をするのよいでしょう。
2級試験で重要なのは、民法と商法・会社法です。100点満点のうち、およそ35~50点が民法と商法・会社法の分野に関わる問題が出題されています。そのため重点的に力を入れて学習をすることがおすすめです。
ビジネス実務法務検定2級の独学はできる?不安な場合は通信講座を!
ビジネス実務法務検定2級は独学での資格取得も可能です。しかし、合格率が安定しないことからわかるように、傾向と対策が必要な試験といえます。
勉強時間の目安は70~100時間くらいです。自分で学習計画を立てることが不安な方や、市販のテキストをひたすら読み暗記をする学習法が向いていないと思う方には通信講座を利用しましょう。
スタディングのビジネス実務法務検定講座ならオンラインですべて学習が可能なため、忙しい方にもスキマ時間での学習におすすめです。わかりやすいビデオ講座やIBT試験(2021年よりビジネス実務法務試験の受験方法がオンラインでの受験となりました)の対策もしっかり行えます。
無料講座のお試しもできますので気になる方はぜひご覧ください。
| コース名 | 3級・2級セットコース |
| 税込み価格 | 19,800円 |
| 受講形式 | オンライン |
| 教育給付金制度 | 2021年版:2022年1月31日まで 2022年版:2023年1月31日まで |
| 特典や割引 | 調査中 |
| 受講者の合格率 | |
| 公式サイト | スタディング公式 |
ビジネス実務法務検定1級の難易度は?

3級、2級と試験の難易度は上がることがわかりました。では1級の難易度はどの程度になるのでしょうか。
ビジネス実務法務検定1級は難易度が高い試験です。合格率は大きく下がり、2級の合格者であっても1級の合格には100時間程度の勉強時間が必要となります。
1級の出題内容や合格率など詳しく見ていきましょう。
1級の出題内容は?毎年ほぼ同じ形での出題
ビジネス実務法務検定1級レベルは、「業務上必要な法務知識をビジネス全般にわたって持っており、その知識に基づいて多面的な観点から高度な判断・対応ができること」を基準として設定しています。
受験ができるのは2級合格者のみですので注意しましょう。
1級の試験内容はほぼ定型化されています。出題内容は下記の通りです。
- 2級および3級の出題範囲に該当する法律および関連法令が出題
- 共通問題→民法および商法を中心にできるだけ全業種に共通して発生することが考えられる法律実務問題を出題
- 選択問題→特定の業種に関連する法律や事例による実務対応能力の試験です。法務実務担当者が遭遇するさまざまな場面を想定した問題が出されます。
1級の合格率は?約10%前後(偏差値66程度)
2019年のビジネス実務法務検定1級の合格率は17.2%でしたが、それまでは約11%の低い数字で合格率は推移しています。
また偏差値は66程度とみなされ、難易度は社労士や中小企業診断士と同程度となります。論述式の試験であり難易度の高い試験です。
1級の合格基準は?各問題5割以上かつ全体で7割以上の得点
試験は論述式で行われます。制限時間は共通問題、選択問題ともに2時間です。
共通問題2問・選択問題2問の200点満点とし、各問題ごとに得点が50%以上でかつ合計点が140点以上をもって合格となります。
ビジネス実務法務検定はどれから受けるべき?難易度を踏まえて検討しよう!

ビジネス実務法務検定をどの級から受けようかと迷う方もいるでしょう。
合格率の高い3級から受けるべきか、またはいきなり2級を受験しても合格は可能なのか説明します。
ビジネス実務法務検定を取得することで活かせる場面はどこにあるのでしょうか。今後自分の目指すところがどこにあるのかで受ける級も変わりますのでぜひ参考にしてみてください。
ビジネス実務法務検定の級と活かせる場面
ビジネス実務法務検定の3級・2級・1級はそれぞれどのような場面で活かすことができるのでしょうか。
- 現在の仕事で活かす場合・・・法務関連の業務はもちろん、ビジネス実務法務検定の知識は営業や販売、総務や人事など幅広い業務で必要です。さまざまな場面で活かすことができるといえます。
- 3級・・・就職・転職時のアピールポイントとして活用することができます。よりスキルアップを目指すのであれば2級の取得が好ましいです。またプライベートの中でも法律の知識があることで役立つ場面が多くあります。
- 2級・・・弁護士などの外部専門家への相談対応など、実務でも使える法務の専門知識を取得できます。法務の業務をされている方には、2級を取得することで仕事の幅をより広げることが可能です。
- 1級・・・より専門性を持ち法務部門の責任者として活躍ができます。
いきなりビジネス実務法務検定2級から受けられる?
2級から受験をすることは可能です。
法律の勉強を少しでもしたことがある人であれば、いきなり2級を受験しても問題ありません。しかし、法律の勉強を全くしたことがない人は3級のテキストを一読してから2級の勉強をはじめるのがいいでしょう。
3級の受験を飛ばし、いきなり2級を受験するメリットは時間やお金の節約になることです。しかし、難易度は3級よりも上がりますのでしっかりと計画を立てて学習を行いましょう。
1級受験にはビジネス法務エキスパートの資格が必要
2級に合格するとビジネス法務エキスパートという称号が与えられます。ビジネス法務エキスパート所持=ビジネス実務法務検定2級合格者ということです。
1級受験には2級の合格が受験資格となりますので1級までの飛び級はできません。2級を取得してから1級の合格を目指しましょう。
ビジネス実務法務検定を受験したい!申し込みから受験までの流れ

ビジネス実務法務検定の申し込み手順は次のとおりです。
- インターネット申し込み
- 自宅や会社、あるいはテストセンターで受験
- 当日は本人確認を進めてから受験
受験を予定されている方は当記事で詳しく申し込みから受験まで解説します。
申し込み前に知っておきたいこと
ビジネス実務法務検定は7、12月に実施される試験です。インターネットで受験でき、次の場所で受けられます。
- 全国各地のテストセンター(CBT方式)
- インターネット環境がある自宅や会社など(IBT方式)
基本的にはいつものパソコンで受験できるIBT方式がおすすめです。自宅やオフィスなどいつもの環境で受験できます。もしネット環境に不安がある場合には、全国各地のスクールで受けられるCBT方式を選びましょう。
申し込みの際には検定級によって受験料がかかります。
| 検定級 | 受験料(IBT方式) | 受験料(CBT方式) |
|---|---|---|
| 1級 | – | 12,100円(税込)※12月のみ開催 |
| 2級 | 7,700円(税込) | 9,900円(税込) |
| 3級 | 5,500円(税込) | 7,700円(税込) |
受験方式によって料金が変わるため注意が必要です。テストセンターで受験するCBT方式では、若干割高な料金がかかってしまうため、できる限り自宅でできるIBTを選択しましょう。
1級を希望する方は、CBT方式(統一試験)のみ受けられます。12月に統一試験が開催されるため受けたい方は期間に合わせて申し込みしましょう。
申し込み方法
ビジネス実務法務検定の申し込み方法は次のとおりです。
- インターネットから申し込み
- 受験日時を選ぶ
- 支払方法(クレジットカードorコンビニ)を選ぶ
- 申し込み完了
インターネットから申し込めるため、都合の良い時間に進めましょう。IBTやCBT方式どちらも同じ申し込み方法です。申し込みの際には、別途東京商工会議所オンライン試験プラットフォームへの登録が必要になります。
申し込みボタンから、受験日時を選択後に受験料を支払うため、クレジットカードなどを手元に用意しておきましょう。コンビニ決済も可能なため、お好きな支払方法を選びます。詳しい申し込み方法は公式サイトをご覧ください。
1級の受験を希望される方は、すでに受験日時が決まっているため事前に確認しましょう。
受験日当日の流れ
自宅や会社などで受験できるIBT方式を選択された方は、当日の流れは次のとおりです。
- 受験時間になったら、パソコンを開く(タブレットは不可)
- 指定された受験サイトを開き、ログインする(Google Chromeのみ可能)
- 受験する検定級や受験日時を選択する
- パソコンに付属するカメラを使って、本人確認などを行う
- 試験開始
試験前に事前にパソコンの周辺環境を整えましょう。受験できる機器はパソコンのみです。タブレット、スマートフォンや、GoogleChrome以外での受験はできないため注意しましょう。また、受験の際にはカメラやマイクで本人確認があります。基本的には試験中はカメラやマイクで録画されるので、余計な個人情報は映らないように配慮すると良いでしょう。
IBT方式ではカメラやマイクがないパソコンでは受験できません。他のパソコンを用意するか、CBT方式の受験を選択しましょう。
テストセンターで受験できるCBT方式を選択された方は、会場にパソコンが用意されています。別途用意するものはなく、会場にそのまま行けば受験が可能です。受験の際には、会場で本人確認があります。受付で身分証明書類を提示する必要があるため、パスポートや運転免許証などを持参しましょう。
CBT方式では会場のスタッフの指示に従って、試験を進めていきます。
ビジネス実務法務検定の対策方法
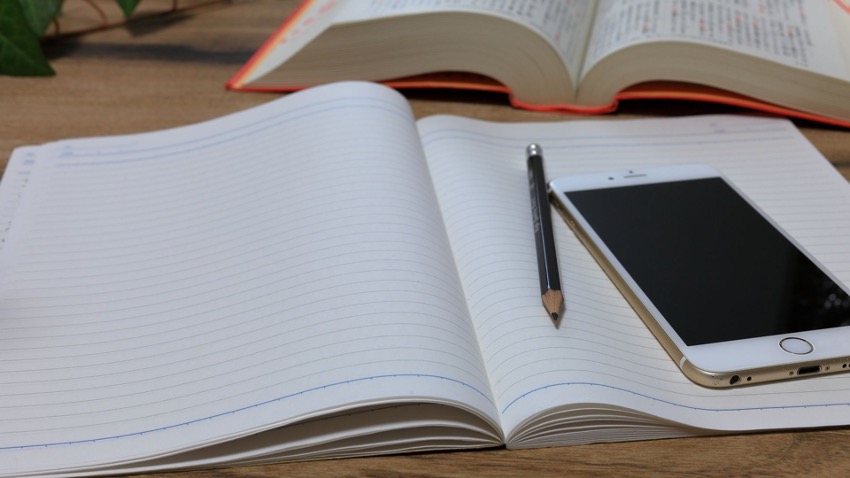
ビジネス実務法務検定では、対策テキストや過去問題集で勉強できます。独学でも勉強を進められますが、法律用語が多いこの検定では学習の仕方も工夫が必要です。
勉強の進め方にお悩みの方に向けて、ここでは対策方法を紹介します。
おすすめ対策テキストは?予備校が出しているものがベター
ビジネス実務法務検定を勉強するなら、資格に強い予備校が出版しているテキストがおすすめです。
①ゼロからスタート! 武山茂樹のビジネス実務法務検定試験1冊目の教科書
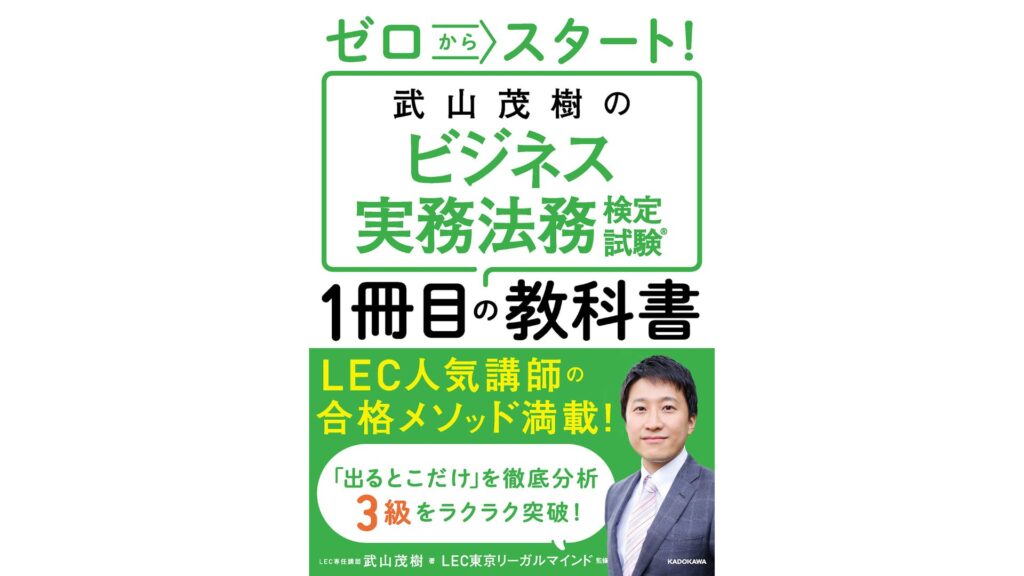
法律や公務員に強いLECが出版する初心者におすすめの対策テキストです。
- カラーテキストですぐに理解できる
- これからビジネス実務法務検定を勉強する方におすすめ
- 難しい法律論を講師がわかりやすく解説してくれる
すべてのページがカラーテキストになっているため、これからビジネス実務法務検定を勉強する方に最適です。また、法律用語に苦労されている方もこのテキストですぐに理解できます。現役弁護士がわかりやすく解説してくれるため、安心して勉強を進められます。はじめて学ぶ方はこのテキストから学びましょう!
②ビジネス実務法務検定試験(R) 一問一答エクスプレス 3級 2022年度
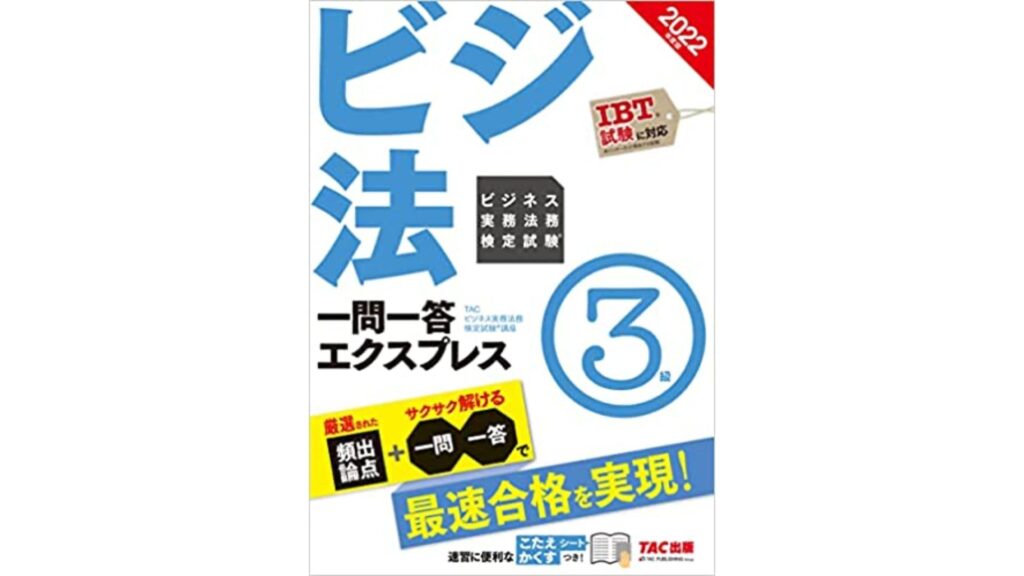
資格に強いTACが出版している一問一答テキストです。
- 出題頻度が多い問題をすぐに確認できる!
- 体系別に構成されているので、わかりやすく読める!
- 簡潔な解説で、理解しやすい
合格に向けてさらに知識を身につけたい方におすすめなのが一問一答テキストです。シンプルな構成で気になる問題をすぐに確認できます。不安な箇所はすぐに暗記も可能です。出題頻度が多い問題を中心に掲載しています。一問一答対策で試験本番も安心です。
公式テキストは独学には向かない
公式テキストで独学を進めることは可能です。しかし、2級以上は難しい法律用語が問われるため、独学ではどうしても多くの勉強時間を確保する必要があります。
管理職以上でビジネス実務法務検定の受験を予定している方は、本業で勉強時間が確保しづらいかもしれません。そこで、予備校の通信講座で効率良く勉強を進めましょう。通信講座ではあれば、最短での合格を目指せるためとてもおすすめです。
何を勉強すればいい?問題集を繰り返し解こう
ビジネス実務法務検定では、ビジネス全般に関するあらゆる法律論が出題されます。法律用語は一度聞いただけでは覚えづらいため、繰り返し問題を解きましょう。
2級では弁護士と法律論で相談できるレベルが求められます。まずは対策テキストや過去問題集でしっかりと知識を身につけることが大切です。過去問題集は公式テキストをはじめ、予備校からも手に入ります。
予備校の過去問題集では、出題頻度が多いものを中心に掲載されているので、効率良く勉強が可能です。テキストでお悩みの方は予備校のテキストを検討しましょう。
独学が不安な場合は?通信講座がある
「すぐに資格が欲しいけど、勉強時間があまりない…」そんな悩みを持つ受験者も多いはずです。そこでお勧めしたいのは予備校の通信講座です。通信講座では次の3つのメリットがあります。
- 自宅や通勤など、スキマ時間に勉強できる
- 自分のペースで進められる
- 実績のある講師がわかりやすく教えてくれる
法律用語が多いビジネス実務法務検定では、理解が進まずに悩んでしまうかもしれません。そんな状況でも通信講座ではわかりやすく解説してくれるため安心です。実績のある講師が受験者のために教えてくれます。時間がないビジネスパーソンでも、スキマ時間に効率良く勉強できるので、通勤やカフェでしっかり勉強が可能です。
ビジネス実務法務検定のおすすめ通信講座は下記のとおりです。スタディングの通信講座ではいつものスマートフォンで手軽に学べます。格安の講座で、手軽に学習できるのがスタディングの強みです。効率良く学びたい方はオンラインで学べる通信講座がおすすめです!
| コース名 | 3級・2級セットコース |
| 税込み価格 | 19,800円 |
| 受講形式 | オンライン |
| 教育給付金制度 | 2021年版:2022年1月31日まで 2022年版:2023年1月31日まで |
| 特典や割引 | 調査中 |
| 受講者の合格率 | |
| 公式サイト | スタディング公式 |
そのほかビジネスシーンで使える資格は?おすすめ資格を紹介!
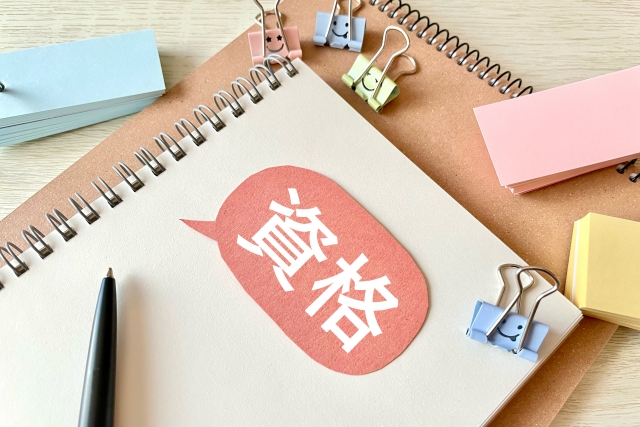
ビジネス実務法務検定以外にもビジネスパーソンが持っておくと有利な資格がいくつかありますので紹介します。
詳しく解説がされた記事がありますのでぜひ参考にしてみてください。
- ビジネス会計検定
財務諸表の分析できる能力を身に付けられるビジネス会計検定に関する記事は、ビジネス会計検定試験の難易度は?合格率から勉強のコツまで詳しく解説!にて級ごとの合格率や試験概要など詳しく解説されています。
- コンプライアンス検定
ビジネスにおいてコンプライアンスに関する知識を身に付けられ、ビジネスの現場全体で活かすことができる資格です。ビジネスコンプライアンス検定とは?ビジネスに役立つ資格の難易度を解説にて詳しく解説されていますのでご覧ください。
- ビジネスマナー検定
ビジネスにおけるマナーを身に付けらるビジネスマナー検定は、職種問わずビジネスシーンに役立ちます。ビジネスマナー検定には種類がありますので、ビジネスマナー検定とマナープロトコール検定の違い!合格率や難易度は?にて違いや試験について詳しく紹介されています。
ビジネス実務法務検定の難易度は級によって大きく違う!自分に合った級から始めよう!

ビジネス実務法務検定は級により大きく難易度が変わります。法律の勉強が始めての方であれば3級からの取得が好ましいです。テキストをまんべんなく読めば確実に合格を狙えるでしょう。
2級になると難易度は少し上がりますので計画的な学習が必要となります。独学での合格も決して不可能ではありません。1級は合格率10%前後となり、3級、2級と比べかなり難しい試験と言えます。スキルアップのために取得できれば大きな自信につながるでしょう。
法律を学ぶことはビジネスシーンははもちろん、生きていくうえであらゆる不利な状況を判断、回避することができ、自分を守ることにもなります。ビジネス実務法務検定を受験する際には、自分に合った級から始めていきましょう。







コメントを残す